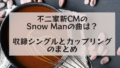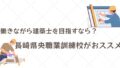大雨や台風の予報を聞くたびに「もし避難が必要になったら、愛犬はどうしよう?」と不安になる方は多いのではないでしょうか。
実際、ペットがいるために避難をためらうケースは少なくありません。
こんなとき、長崎県では、愛犬と一緒に安全に避難するためのルールやガイドラインが整備されてるので知っておくと安心です。
同行避難や同伴避難、分散避難といった避難方法、住んでいる自治体の受け入れ状況、そして事前に準備しておくと役立つグッズやしつけ。
こうした知識と準備があれば、いざ愛犬と避難、というとき不安は解消され、勇気をもって行動できます。
この記事では、長崎県内で愛犬と避難するための最新情報を、わかりやすくまとめました。
※長崎県外にお住まいの方は、長崎県内に住んでいるお身内やお知り合いに愛犬と一緒に避難する方法をお伝えくださいね。
「愛犬を置いて避難なんて絶対無理…」長崎県の同行避難制度と心の準備で安心避難
いざ避難指示が出たとき、「愛犬だけ家に残すなんて考えられない…」って思うのは、当たり前です。
家族同然の存在なんだから、一緒にいたいって思うのは、飼い主さんなら誰もが感じる自然な気持ちです。
でも、安心してください。
長崎県には、愛犬と一緒に避難できる制度がちゃんとあります。
災害時には、いろいろな情報の中から自分で考えて行動しなきゃいけないです。
避難行動の中には「愛犬と一緒に避難する方法」もしっかりと整っているのです。
ここでひとつ、知っておいてほしいのが愛犬との避難方法の「同行避難」と「同伴避難」の違いです。
同行避難と同伴避難
同行避難:避難所まで一緒に移動できるけれど、避難所では人間とペットは別々のスペースで過ごすことになります。
同伴避難:避難所でペットと人が同じスペースで過ごせる避難行動。
実は、長崎県では愛犬との避難は「同行避難」が基本となっているため、避難所では愛犬と離れ離れ。
お互いに不安を感じるかもしれませんが、大事なのは災害から愛犬を守ること。
一緒に避難できて無事を確認できる場所にいることこそが重要なんです。
長崎県では、避難所でのペット受け入れ対応マニュアルや災害時動物救護対応ガイドラインも整備し、自治体と獣医師会の連携体制も構築されています。
そういう意味でも、避難所に愛犬と同行避難をするというのは安心安全の策といえます。
もちろん、同行避難を成功させるには私たち飼い主側の日頃の準備も欠かせません。
たとえば、
愛犬がケージやキャリーに慣れている
基本的なしつけができている、
そして何より「一緒に避難する」という強い気持ちをもって冷静に行動できるようにしていきたいですね。。

「愛犬を避難所に本当に連れて行けるの?」長崎県自治体の対応と備え
「避難所でペットを受け入れてもらえるのかしら…」という不安、よくわかります。
地域によって対応に差があるのは事実ですが、長崎県内の多くの自治体で受け入れ体制が整ってきています。
調べてみると「同伴避難」を認めている避難所は数が少ない傾向です。
避難所の状況は災害の規模や施設によって変わることもあります。
長崎市は通常は「同行避難」を認めていますが、過去に台風が来たとき「居住スペースに入れない犬などが暴風に巻き込まれる可能性がある」(防災危機管理室)と断わられたというケースもありました。
しかし、長崎市では令和7年6月現在、試験的に同伴避難を認めている避難所もあるようです。
このように、刻一刻と愛犬との避難に関する情報は変わっていくので、事前の確認と準備を怠らないように。
まずは、住んでいる市町村のホームページで災害時のペット対応について調べてみてください。防災担当課に直接問い合わせするのもいいですね。
「うちの地域では犬と一緒に避難できる場所はありますか?」と聞いてみれば、きっと丁寧に教えてくれるはずです。
そして、避難セットの準備も忘れずに。
ケージやキャリーバッグ、フード、水、食器、トイレ用品、首輪とリード(予備も含めて)、お気に入りのタオルやおもちゃ、普段飲んでいる薬があれば、それも一緒に。
これらを一つのバッグにまとめておけば、いざというときに慌てずに済みます。
避難セットについては、この後詳しく説明しますね。
「今すぐ何を準備すればいい?」愛犬を守る避難セットと避難行動の順序
避難の準備は、難しく考えなくて大丈夫。
普段から、少しずつ「万が一」に備えていけばよいです。
避難時を想像して、少しでも不自由しないように、って考えて準備するのです。
まず用意したい避難セットの中身。
そして十分な水や食料の他、薬等も用意し、避難所への避難ルートを確認しておく等、
いざというときに慌てないように、愛犬に基本的なしつけをし備えるのが重要です。
具体的には以下のものを準備
基本セット(避難バッグに常備)
-
キャリーケースまたは折りたたみケージ(普段から慣れさせておく)
-
リード・首輪(名札付き・予備も含めて2セット)
-
ペットフード・水(最低3日分、できれば1週間分)
-
食器(軽量で割れにくいもの)・給水ボトル
-
トイレ用品(ペットシーツ、うんち袋、消臭スプレー、紙パンツ)
-
タオル・毛布
-
常備薬・予防薬
-
写真(迷子になった時の身元確認用)
-
お気に入りのタオルやおもちゃ(ストレス軽減のため)
- 療法食や常備薬(かかりつけの獣医師と相談)
あると助かるもの
-
ペット用防災ベストやレインコート
-
折りたたみ式ペットカート(高齢犬や長距離移動用)
-
使い捨て手袋・ウエットティッシュ
購入できる場所(長崎県内)
-
ホームセンター(コメリ、ナフコ、コーナンなど)
-
ペットショップ(アミーゴ長崎店、ペットワールドアミーゴ諫早店 ほか)
-
ドラッグストア(一部でペット用品取扱あり)
-
ネット通販(災害時は在庫切れになることもあるので事前購入がおすすめ)
長崎県内おすすめショップマップ
避難するときは、ペットと一緒に避難(同行避難)できるよう、日頃からキャリーバックやケージに入ったりして慣れさせておくことも必要です。
週末にキャリーに入れてちょっとしたお出かけをしたり、ケージを居心地の良い場所にしてあげたり、工夫し楽しみながら慣れさせてほしいです。
ケージに入るといいことがある、と思わせるのが大事ですね!
しつけについても、「待て」「お座り」「来い」などの基本コマンドができれば十分。
避難所では多くの人が集まります。
愛犬が落ち着いて過ごせるよう、日頃から人や他の動物に慣れさせておくことも大切です。

避難行動の順序
いざ災害が起きたときの行動順序も頭に入れておきましょう。
まず何よりも自分自身の安全確保が最優先。
災害が起こったときに最初に行うことは、飼い主自身や家族の安全確保。
自分自身や家族が安全でなければ愛犬も安全にできないのです。
急には冷静に行動できないこともあるので、普段から考え備えておく必要があります。
自分の安全が確保できたら、愛犬をキャリーやケージに入れて、準備しておいた避難グッズを持って避難開始。
避難ルートは事前に歩いて確認しておき、愛犬にとって負担の少ない道を選んでくださいね。。
避難所に着いたら、係の人の指示に従って愛犬の居場所を確保。
避難所等においては、自治体の指示に従い、ルールを遵守し、他の避難者に迷惑をかけないよう気を配ります。
もしかしたら、周りに動物が苦手な方やアレルギーのある方がいらっしゃるかもしれません。
思いやりの気持ちを持って過ごしたいものですね。
フォローしておくと安心な公式防災アカウント
※基本的にxのアカウントですが、xを運用していない自治体もあります。
| 自治体 | アカウント名 | ユーザー名 | 主な発信内容 |
|---|---|---|---|
| 長崎県 危機管理課 | 長崎県防災・危機管理課 | @ngs_kikikanri | 災害時の避難情報、防災啓発 |
| 長崎市 | 長崎市防災危機管理室 | @nagasakibousai | 避難所開設、警報情報 |
| 佐世保市 | 佐世保市役所 | @SaseboCity | 市政情報や緊急情報等 |
| 島原市 | 島原市 | 市政情報やイベント情報 | |
| 諫早市 | 諫早市防災 | 防災情報など安全・安心に関する情報 | |
| 大村市 | 大村市役所 | Facebookページ | 災害時の緊急情報、避難所案内 |
| 平戸市 | 平戸市防災 | ホームページ | 台風・地震時の情報 |
| 松浦市 | 松浦市・防災情報 | ホームページ | 防災情報 |
| 対馬市 | 対馬市役所 | ホームページ | 防災情報 |
| 壱岐市 | 壱岐市防災 | @IkiCity | 気象・災害発生・防災・危機管理 |
| 五島市 | 五島市 | ホームページ | 台風情報、避難所案内 |
| 西海市 | 西海市役所 | ホームページ | 防災・緊急情報 |
| 雲仙市 | 雲仙市公式 | @unzen_official | まちネタ・防災情報 |
| 南島原市 | 南島原市防災ポータルサイト | 南島原市防災ぽポータルサイト | 緊急情報・避難所開設など |
地域別ペットとの同行避難について
→市町村別避難所の詳細と問い合わせさ先(令和7年6月2日作成)
まとめ
災害時に「愛犬を連れて避難する」という選択は、長崎県ではもはや特別なことではありません。
制度として確立された同行避難のルールがあり、長崎県の各自治体でも受け入れ体制が整備されています。
期待しているような環境ではないかもしれません。
でも、「一緒に避難する」ことは必ずできます。
愛犬との避難は準備が大事ー長崎県
大切なのは、日頃からの心構えと準備です。
住んでいる市町村の防災情報をチェックし、愛犬用の避難セットを用意し、基本的なしつけを身につけさせる。
そして何より「この子は家族だから、絶対に一緒に避難する」という強い気持ちを持つこと。
具体的には、
市町村の公式ウェブサイトや防災担当課の連絡先をスマホにブックマークしておく。
愛犬がケージでの移動に慣れるよう日常的に練習するなどの準備です。
災害を完全に防ぐことはできませんが、愛犬を守る方法はいくらでも準備できます。
「もしものとき」を想像するのは不安かもしれませんが、その不安を「準備」に変えていけば、きっと心強くなっていくはず。。
大切な家族の愛犬と、あなた自身の命を守るために。
長崎県で暮らす私たちみんなで、準備をしていきましょう。
一日でも早く始めた方がいいですね!